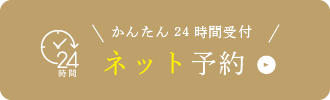こんにちは!高松市の高田歯科口腔外科医院の高田です。
歯を失ってしまい、インプラント治療を検討されている方の中には、骨粗しょう症を患い、その治療薬を服用されている方もいらっしゃるかと思います。「薬を飲んでいるから、インプラントは無理なのでは?」と不安に思われるかもしれません。
結論から申し上げますと、骨粗しょう症の治療薬を服用している方がインプラント治療を受ける際は、いくつかの注意点があります。今回は、骨粗しょう症の治療薬がインプラント治療にどう影響するのか、そして安全に治療を受けるために知っておくべきことについて、詳しくお話しします。
骨粗しょう症は、骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気です。この治療には、骨の密度を保つためのさまざまな薬が使われます。特にインプラント治療との関連で注意が必要なのは、以下の2種類の薬です。
- ビスフォスフォネート製剤(BP製剤)
ビスフォスフォネート製剤は、骨の吸収を抑え、骨密度を上げるために広く使われている薬です。注射薬と内服薬があり、骨粗しょう症の他に、がんの骨転移の治療にも使われます。
この薬の最大の問題点は、ごく稀にですが、顎の骨の代謝を抑制し、顎骨壊死という重篤な合併症を引き起こす可能性があることです。顎骨壊死とは、顎の骨の血流が悪くなり、骨の一部が死んでしまう病気です。
インプラント手術は、顎の骨にインプラント体を埋め込む外科的な処置です。この手術の際に、ビスフォスフォネート製剤の影響で骨の治癒がうまくいかず、顎骨壊死のリスクが高まることが指摘されています。
- デノスマブ(プラリア®)
デノスマブは、骨の吸収を抑制する新しいタイプの骨粗しょう症治療薬です。6ヶ月に1回の皮下注射で、ビスフォスフォネート製剤と同様に、インプラント治療の際に顎骨壊死のリスクを高める可能性があります。
治療を安全に進めるために、まずすべきこと
骨粗しょう症の治療薬を服用されている方がインプラント治療を安全に受けるためには、以下の2点が非常に重要になります。
- 歯科医師への情報提供
インプラント治療の相談をする際には、必ず歯科医師に以下の情報を正確に伝えましょう。
・骨粗しょう症の診断を受けていること
・服用している薬の名前(ビスフォスフォネート製剤、デノスマブなど)
・治療薬の投与経路(内服薬か注射薬か)
・治療期間(いつから薬を飲んでいるか、注射をしているか)
特に、注射薬の場合は内服薬よりも顎骨壊死のリスクが高いとされていますので、正確な情報が不可欠です。
- 内科医・主治医との連携
インプラント治療を開始する前に、歯科医師は患者さんの内科の主治医に病状照会を行います。これにより、インプラント治療が患者さんの全身の健康に悪影響を与えないか、また、顎骨壊死のリスクを避けるために、一時的に薬の服用や注射を休止すべきかなどを確認します。
患者さんご自身も、歯科治療を受ける予定があることを主治医に伝え、事前に相談しておくことをお勧めします。
歯科医師は、主治医からの情報をもとに、インプラント治療が可能かどうかを慎重に判断します。
治療が可能なケース
薬の服用歴が短い: ビスフォスフォネート製剤の内服薬で、服用期間が短い場合など、リスクが低いと判断されれば、インプラント治療が可能となる場合があります。
投薬を休止できる場合: 主治医の判断で、インプラント治療の前後で一時的に薬の服用を中止できる場合は、リスクを下げて治療を進めることが可能です。これを「ドラッグホリデー」と呼びます。
治療が難しいケース
薬の服用歴が長い: 長期間にわたりビスフォスフォネート製剤を服用している場合や、注射薬を使用している場合など、顎骨壊死のリスクが高いと判断されると、インプラント治療は行わない方が良いと判断されることがあります。
この場合、インプラント以外の治療法、例えば入れ歯やブリッジなど、顎の骨に負担をかけない治療法を検討することになります。
まとめ
骨粗しょう症の治療薬を服用されている方がインプラント治療を検討する際は、治療が可能かどうかを自己判断せず、必ず歯科医師と主治医に相談することが最も重要です。
・治療前に、服用中の薬や治療歴を歯科医師に正確に伝えましょう。
・安全に治療を進めるため、歯科医師と主治医の連携が不可欠です。
・リスクが高い場合は、インプラント以外の治療法も視野に入れましょう。
当院では、患者さんの全身の状態を考慮した上で、安全なインプラント治療をご提供しています。骨粗しょう症の治療薬についてご不安な点があれば、まずは当院にご相談ください。
皆様のお口の健康、そして全身の健康をサポートできるよう、全力でサポートさせていただきます。